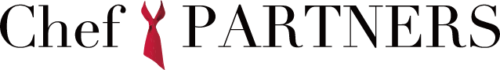
「シェフパートナーズ 料理塾」配信に寄せて
日本人の薬食い
食べるということは色々な要素があります。
まずは美味しいものを食べる。
コミュニケーションをはかるために食べる。
行事食として食べること伝えていくことなど、諸々あります。
そして一番大事な健康維持、生命維持ということになりますと、私たち日本人は米食です。
米を食べるためにどのような食事を行なってきたか、それは元々野菜をたくさん食べながら「薬食い」をしてきたというのが、私たち日本民族でありました。
1月7日の「七草」から始まり、多種多様な野菜を栽培して、それに自然に自生しているものを加えながら食べてきた文化があります。
コメとトラブルに
それがいつしか、脂肪をたくさん摂取する欧米の食文化を取り入れるようになり、米とトラブルを起こすことになりました。
素早くその98%が消化される米ですが、その米の糖化の早いことが今は悪者になっています。
米は糖化した途端に酸性食品になりますが、私たちの祖先は、こんにゃくや牛蒡、海苔などの自然の食品を米と一緒に摂ることで、体をアルカリ性に中和しながら「薬食い」してきました。
近年、日本人の寿命は延びましたが、それにつれて病気も増えてきてしまったことに対して、我々がどういう対処をすべきかといえば、結局は野菜を食べることです。
野菜を食べることが良いことは、今では誰もが知っていることですが、食物が生産地から貴方のお口に入るまで、近道で食べるということが重要なのです。
命の入り口
いま私たちは、命の入り口をどうするか、ということを真剣に考えるべきだと思います。
できれば生産地からお口に入る距離をなるべく「近道」にする。
既製食品というのはその距離が長すぎます。
鮮度の良い野菜を簡単な調理方法でお口に入れる。
たとえばブロッコリーを80度くらいで茹でる。これは完全に加熱をするんではなくて「酵素を動かしながら食べる」ということです。
ブロッコリーやカリフラワー、蕪であるとか、小松菜も低温で茹でる。 それぞれに適した火の入れ方があります、薬で摂るのではなくて、食べ物で摂ることが大切です。
なぜ食べ物で摂るのが大切と申しますと、食べる行為というのは口の中で咀嚼します。
咀嚼することによって唾液が出ます。その唾液がガン細胞を殺し、ガン予防になるという風にも言われております。
ですから、食べること_命の入り口をどういう風に大切にするかということを考えて、鮮度の良い食材を食べていただきたいなと思います。
これが、日本人の本来の健康法だと思います。
シェフパートナーズ料理塾では、現代の「薬食い」を仲間のシェフ、料理人たちとご紹介していきたいと思います。
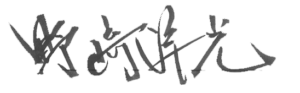 シェフパートナーズ 会長
シェフパートナーズ 会長
シェフパートナーズ 料理塾プレスリリース































